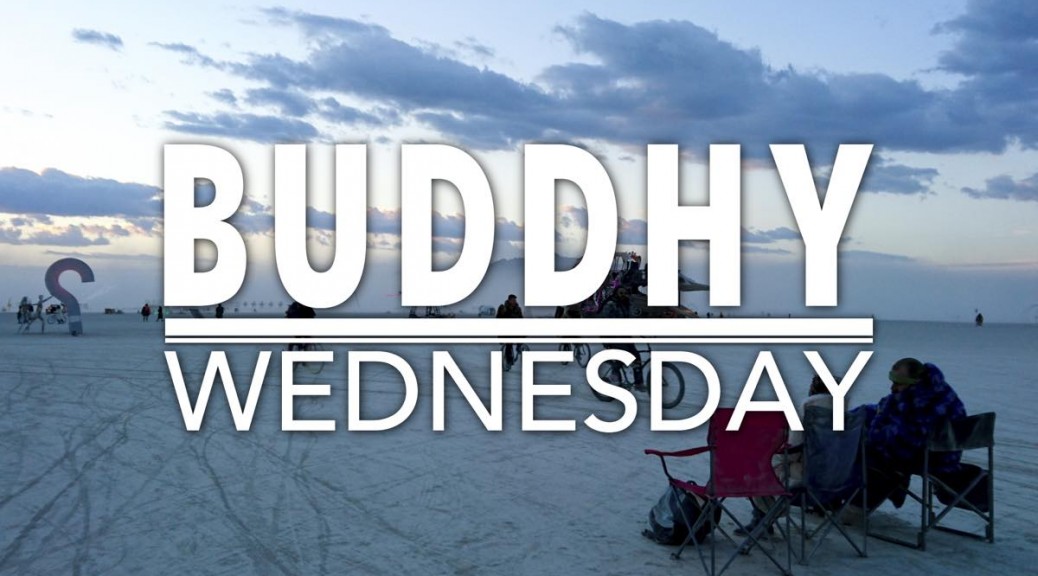アメリカ・ネバダ州リノの郊外約150キロに位置する砂漠で毎年8月末~9月あたまに開催されているフェスティバル「バーニングマン」に参加してきた。
http://www.earth-garden.jp/goodlife/52149/
渡航前に知識はあったものの、やはり現地に赴いて初めて実感したのは、北米大陸の環境の苛酷さだった。会場となるブラックロックシティの広大な砂漠の上では、太陽の熱を遮蔽するものがない。
日中は強烈な日射しが照りつけ、体感温度40度近くまでなるが、19時を過ぎてだんだん陽が落ちてくると、気温が急激に、それはもう急速に下がってくる。19時30分、いよいよ日没の頃には、太陽の側から強風が吹きつけてくる。その砂嵐で眼前がホワイトアウトして、風が去ると辺りは漆黒の闇を迎えている。

いよいよ祭りは盛り上がりをみせ、参加者は思い思いに発光グッズとライトを身につけ、遊びへと繰り出す。まるでマッドマックスの世界だ。原野を見渡すかぎり360度、全方位にステージがあって、あらゆるジャンルの音楽が地鳴りのように轟いている。スピーカーに近づきすぎるとあまりの音圧に内臓がえぐられたようになって、吐き気がしてくる。耳がイカレる。それが途中から快感に変わってくる。星空の下、大地の上で踊っていると我を忘れてしまうけれど、宇宙の冷たさがダイレクトに伝わってくるので、気温は低い。夜間はダウンを着ていたほどだ。



夜明け前、会場中央奥に建てられた「テンプル」に立ち寄ると、そこは俗世とは切り離された静謐な領域。人々は想い思いに祈りをささげている。もっとも冥くて寒いこの蘇生前の時間帯に、テンプルには低く唸るようなチャントが聞こえている。

日の出。東の空が大地を照らすと、地上に色彩が戻ってきた。昨日までとはすべてが異なった、全く新しい1日の誕生だ。地表は暖められ、砂塵は神秘的なもやとなって世界を静観している。パーティーフリークたちの踊り明かした夜は終わり、ここからは昼の住人たちの生活が営まれる。持参してきたキッチンでコーヒーを入れ、サンドウィッチをつくる。この地球のどこにいようとも、安心できる朝を迎えられたならばきっと生涯続けていきたい、日々の食卓だ。食べて、遊んで、眠るだけ。

バーニングマンの会場に到着した時、内心では「難民キャンプのようだな」と思った。遥かな岩山に囲まれたこのクレーターのような砂漠の真ん中に、世界中から7万人が集まる。トレーラーやキャンピングカーやテントが何キロにも及んで辺りを埋め尽くしひしめき合い、参加者はここで生活をする。やぐらに登って見渡してみるとここの光景は本当に街のようで、さながら砂漠の真ん中に現れた難民キャンプの様相である。
けれど、自分はすぐにこの見解を恥じた。我々は好き好んでこの苛酷な状況下に身を置きに来たのだ。1週間もすればきっと元の生活が待っている。有限だから耐えられる。寝床まで入り込んでくる砂も、偏った食事も、少し不自由なトイレも、酷暑も極寒も、鳴り止まない音楽も。終わりがあると解っているから、われわれはこの場限りと楽しむことができるのだ。終わりの見えない難民キャンプとは本質が違う。

このバーニングマンの信条の1つは「Leaving No Trace(痕跡を何も残さない)」とされる。会場中央にそびえる巨大なヒトガタ「マン」は、最終日が近づくと燃やされ(バーニングマン、の名前の由来である)、建造物もオブジェもつぎつぎと燃やされていく。会期が終わるとそこには何も残っておらず、元の荒涼とした砂漠に元通りだ。我々がここを去っても、太陽はまた東から昇って大地を焼き付けて、夜には流れ星も降っているかもしれない。森羅万象はひたすらに大きく、美しく、荒く、僕らは謙虚にならざるを得ない。極地だから人恋しくなったり、命の危険と隣り合わせだからこそ素直に他人の優しさに感謝できたりするのかもしれない。

羽田に帰国し、家に着いた頃には26時を回っていた。仮眠をとって早朝、日課としている朝のおつとめに寺の本堂に向かうと、美しさにふるえた。日本の大気はこんなにも柔らかかったのか。朝の空気が湿気を含んでいる。そして身の回りには、なんと多くのマテリアルに溢れていることか。木材の建築にコンクリートの基礎、ガラスの花瓶に漆器の湯のみ、和紙の包みに布の服。境内には玉砂利、裏池には鯉。耳を済ますとさまざまな虫の声が聞こえてくる。この国土の自然環境はなんて多様で且つ繊細なんだろうか。
住んでいる場所、触れるもの、身の回り。自分が望む望まざるに関わらず、わたしを取り囲む自然環境が、わたしを形成しているのだなと心底思えた旅路だった。
http://www.earth-garden.jp/goodlife/52149/