まさか去年できて、今年できないなんて…。ハイライフ八ヶ岳2021は、地域の人と来場者と出店者と出演者とスタッフと、みんなで「来年への延期」を決めた。その経緯はフェスが身につけるべき、コロナ時代のお作法なのではないか。ハイライフ八ヶ岳は、2021年の開催を失ったけど、簡単には得難いモノを得た。
参加者に呼びかけた「コロナ時代のフェスのお作法」

ハイライフ八ヶ岳では、去年から『コロナ時代のフェスのお作法』という言葉を使って、感染対策を呼びかけてきた。この言葉は、ハイライフ八ヶ岳を主催するアースガーデンがコロナ禍を前提にした野外フェスの形を模索するなかで生まれた。
主催者による感染対策はもちろん必要だが、なによりも来場者が自分で考え、適した行動をとってもらわなくては、野外フェスなんて開催できない、ということだ。
実はこれには元ネタがある。フジロックのOSAHOだ。
“ルール・マナー”でもない、規制でもない。快適で気持ちよいフジロックをつくるのは、参加者ひとりひとりの気持ちが大切。国境を越え、文化を越え、フジロックから始まるあたりまえのエチケットを、あえて -OSAHO-(お作法)と呼び、キャンペーンを展開いたします。
“あたりまえ” や “文化” が異なる海外の人に作法を説くのは無理筋だけど「お作法」という言葉は、なんだかいいなと思っていた。
ルールとかレギュレーションよりも、人に委ねる余白がある言葉だ。「大人なんだから、そのくらいわかるよな」ということだし「かっこいい背中を見せてくださいよ」ということでもある。ルールではなく自由を志向する野外フェスにおいて、一人ひとりがちゃんと考えて行動せねばならないのは、コロナに限らず当たり前なのだ。
さまざまな人と決めた「来年への延期」

コロナ時代のフェスのお作法を掲げ、無事に開催を終えた昨年のハイライフ八ヶ岳。でも、今年はダメだった。去年の今頃の自分に教えてあげられるとしたら、どんな顔をするだろうか。
来年に延期した経緯は、こちらの「地域拡大ミーティング」のレポートに詳しくある。( https://hi-life.jp/news/2579/ )地域拡大ミーティングとは、今年や去年生まれたものではなく、開催の初期からやっていたもの。この2年は感染症対策のために広く参加を呼びかけてはいないが、その前は「興味がある人はだれでもウェルカム」だった。
この地域拡大ミーティングのMessengerグループがあり、40人ぐらいが入っている。8割くらいは地域の人だ。開催の可否を決めるにあたり、このグループにそれぞれが自分の思いを投稿した。ちょうどフジロックの開催前後のタイミングだ。お茶の間が「フェス」に対して冷ややかな目を向けだしたころ…。
ぼくのメッセージはこんな内容だ。
いろいろ考えましたが、ぼくの意見は開催支持です。もちろん、地元のみなさんも納得してもらえるなら、ですが。
理由は「今年開催する意義」が、いったん見つかったからです。その意義は「新しいフェスのお作法を、変異株を前提に更新する」ではないかと考えました。
昨年の状況なりにフェスを開催したハイライフが、今年の状況なりにガイドラインをアップデートできれば、今後のイベントや観光業のヒントになり得ると思いました。
もちろんぼくだけではなく、一人ひとりがいろいろ考えた結果「来年への延期」という形で、2021年の開催を断念することになった。
ただし、ただでは転ばぬと、わずか10日ほどで配信企画を立ち上げた。それが「ハイライフ八ヶ岳 AIDラジオ」とクラウドファンディングだ。
もはや、フェスはフェスの中に閉じてはいられない

素晴らしいを配信イベントを終えて、どんな文章を書けばいいか、あれこれ思案した。正直、気が重かった。なぜかというと、今年のハイライフ八ヶ岳を考えるには、野外フェスという枠から抜け出さなければならないと感じていたからだ。
ハイライフ八ヶ岳だけでなく「フェス」はもう「フェス」という枠組みには収まりきらなくなってしまった。広くお茶の間から冷ややかな目で見られ、その開催の是非を問われた。これだけ社会的に注目されてしまったフェスを語るには、もう少し広い目線での総括が必要だと感じていた。
いろいろと考えて思い至ったのは、ハイライフ八ヶ岳2021はその「進め方」を通じてコロナ時代のフェスのお作法」をアップデートできたのではないかということだ。これからのフェスの青写真と言ってもいいかもしれない。昨年と違うのは、示した方向性がフェスの来場者ではなく、他のフェスの主催者や、さらに広く、みんなで何かを決めなければならないときに、その方法のひとつを示せてたのではないか、ということだ。

例えば
– 開催にあたって、その光景を問題提起も含めてレポートしてくれるライターやジャーナリストを募集したこと
– 2021年の開催を断念した根拠を複数明記したこと
– 開催断念を決めた地域拡大ミーティングのレポートを出したこと
– 継続的に「地域拡大ミーティング」という形で、地域の関係者を増やしていったこと
などなど。これを端的に言うと「プロセスが透明であること」と「意思があれば参加できること」だと思う。(とあるスタートアップのCEOをやっている友達から、言葉を引用させてもらった)
人や組織は、何かを決めて動き出さなければならない。しかし、状況は目まぐるしく変わるし、人々の価値観は細分化している。みんなが両手を上げて喜ぶような選択肢はありえない。それでも、なにかを決めねばならない。そんなときに必要なのは、このふたつなんだと思う。
「プロセスが透明であること」と「意思があれば参加できること」を大切にしたからこそ、ハイライフ八ヶ岳は延期となった。

Musicmanに載ったハイライフ八ヶ岳のプロデューサー鈴木のインタビューでも、その経緯や、社会的な考察が語られている。
──5月ごろ開催できた地方野外フェスは複数ある一方で、これから秋に向けて開催予定の各地のフェスの動向も気になります。野外のフェスを開催するにあたり、今後ポイントとなってくるのはどういったことでしょうか。
鈴木:規模と、あと地域のコミュニティとの距離感でしょうね。今時の感覚で言うとコミュニティとの距離感が近い方がいいフェスという感覚があるじゃないですか。僕たちもそういうところでやってるんですけど、今はコミュニティとの距離感が近い方がやりにくいかもしれないです。500人か1,000人くらいのキャパシティで、会場の外にほとんど接点がない状態でポンとやってポンと帰るとかだったらほとんど問題ない。警戒もされず、音の問題さえなければ別にシュッとやってシュッと終わるみたいな感じになるはずなんですよね。これを一番端的に実現してるのは実は富士急ハイランドのコニファーフォレストで、あそこはこの状況下でもアイドルフェスとかを他よりやってると思うんですよね。
──ある意味区切られた場所ですね。
鈴木:そうですね。例えばディズニーランドにあれだけ人が毎日出入りしてても浦安の人たちは不安だって言わないじゃないですか。富士急も同じような環境ですよね。で、なおかつ富士急ハイランドの中にあるので、物理的にも周辺の地域の人とは隔絶していて、距離があるわけで。日常的に数千人レベルの人がバンバン来てる遊園地で、ましてや通常の遊園地の区画とも違うところで運営スタッフも外から来た人がほとんどの状態でパッとやってパッと帰るわけなんで。ハイライフもサンメドウズというスキー場でそういった形でできないことはないんですけど、それがやりたいことかっていうとまたちょっと違う。地域との距離感やバランスは、本当に難しいとこですね。まさか、地域の人たちと隔絶してることがやりやすい要素になっていくなんて2、3年前は誰も予想もしなかったです。
「地域の人たちと隔絶してることがやりやすい要素になっていくなんて2、3年前は誰も予想もしなかったです」。本当に重い言葉だ。
終わりではなく始まりをデザインする
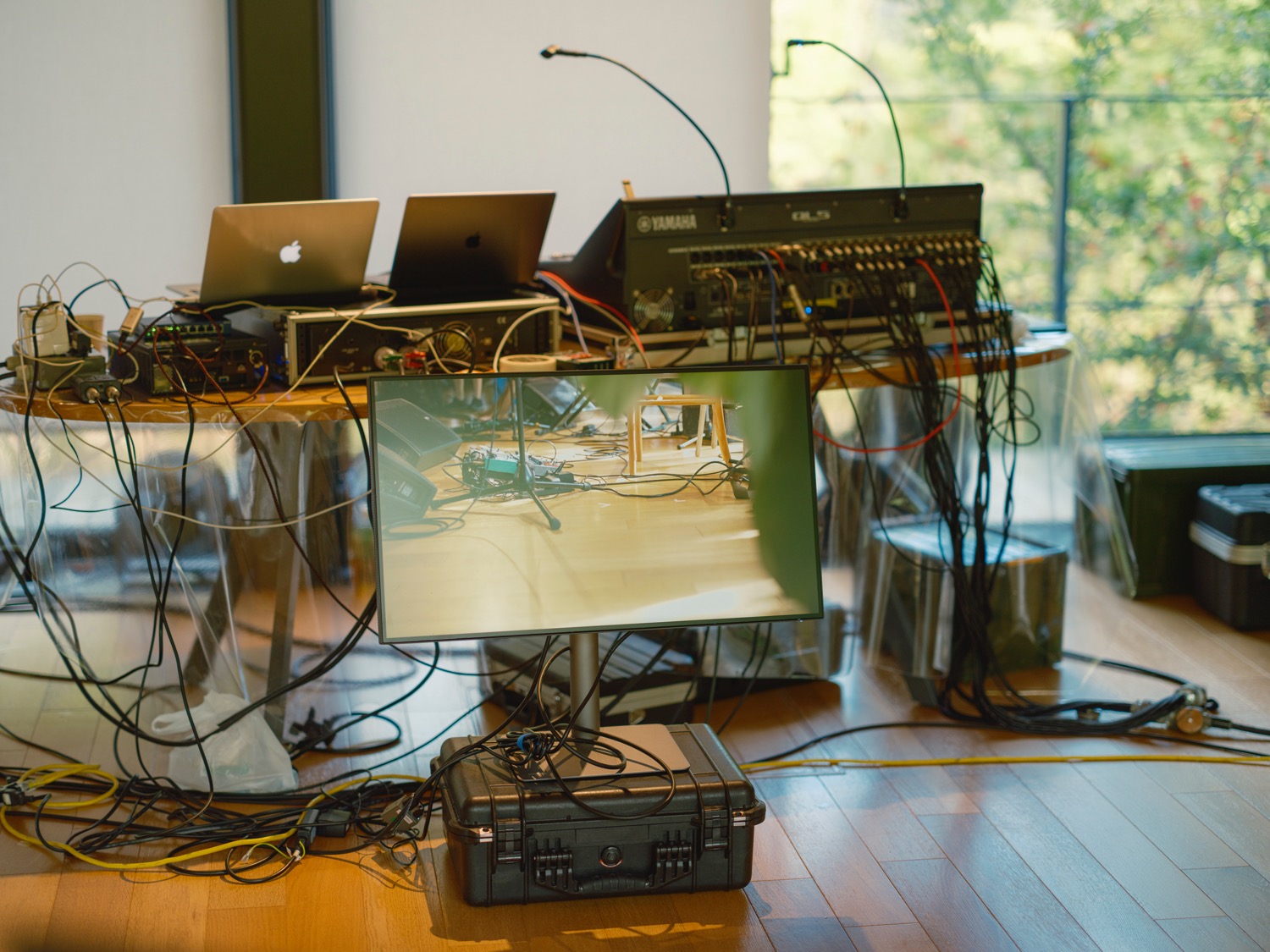
透明性や参加性をあげていくということは、乱暴に言えば非常に効率が悪い。いちいち公開するのはめんどくさいし、たくさんの人が関わってくると判断も煩雑になる。でもハイライフ八ヶ岳はそのプロセスをずっと積み重ねてきた。
そもそも野外フェスとはそういうものなんじゃないだろうか。何かしらの「完成」をつくるのではなく、関わる人や状況によってそのあり方が変わっていく「永遠に未完成」な場。ゴールがなければ、そこに向かうルートも用意されていないので、効率化なんてできない。
Quartzというメルマガの「週刊だえん問答」(有料会員でないと読めません)という連載に面白いことが書いてあった。デザイナーでアーバニストのダン・ヒルさんが、あのブライアン・イーノさんに「街路や路地を文化性を基軸にデザインするにあたってどのような原則が必要か」とアドバイスを求めたそうだ。10個ほどある箇条書きのひとつに、こうある。
建築家ではなく庭師のように考える:終わりではなく始まりをデザインする
野外フェスとは、仮設の街のようなもの。そして、あの偉大な音楽家が街を考えるときに「終わりではなく始まりをデザインする」とアドバイスをした。ぼくにはこの話がフェスの話に聞こえる。
終わりではなく始まりをデザインする、とは例えば「プロセスを開示し、意志があれば参加できる機会をつくる」といった、お作法を立てて、あとは永遠とプロタイプを作りづけるということではないだろうか。
状況に応じて多様に変化し、継続的に場をつくり続ける。それが、コロナ時代のフェスができる背中の見せ方、なのではないか。
コロナ時代のフェスの「青写真」

終わりではなく始まりをデザインするとはいえ、始まりよりももう少し先くらいは見えていたいもの。始まりのもう少し先について、自分の頭では「小回りの効くサイズのものを中心に」くらいにしか考えられてなかったのだけど、プロデューサーの鈴木の考察が身内ながら非常に納得感があるので、ここでも引用したい。
鈴木:ハイライフも自然が豊かな地域環境の中でコミュニティとの距離感が近いフェスなんですけど、これからはどうしても1,000人以下の規模感で考えざるを得ないのかもしれない。来年早いうちに決めていくにはそういう考え方をする可能性もあります。元々3,000人でも大丈夫な会場で、キャパシティをしっかり使って一定の規模を目指すというスタート点があって、ましてや去年の成功を踏まえて2,000人ぐらいまででそんなに文句は言われないだろうと思ってますけど、おそらく今年は開催規模が1,000人でも周りからは反対されたと思うんですよね。ただ、最初から1,000人でやりますと言って、1000人で採算が取れる形を作っていればまた少し違ったかもしれない。
──今後1,000人以下で開催する形を探るとどういった形になりますか。
鈴木:例えば二週連続の週末に渡ってやるとかね。今年の京都大作戦も二週間でやろうとしていたような。要はキャパシティをある程度半分にして採算を取れるようにするっていう意味で、ステージ設営費は一番大きなコストファクターですからね。全体の動員数の合計を細分化していくと気が付いたら10週連続で、もはや野外の常設ステージを作ったみたいになるかもしれない(笑)。
<中略>
僕は自分の著書にも書いてるんですけど、日本に一つくらい常設の野外ステージ、要はゴルフ場ならぬフェス場みたいなのがあってもいいじゃないかってずっと思ってるんですよ。例えば日本だと日比谷の野音はそういう感覚があると思いますし、アメリカだとレッドロックの野外ステージとか、サンフランシスコのショアラインとか、ある意味ニューヨークのセントラルパークの一角とか、常設野外ライブ会場の名所が沢山あるんですよ。サンフランシスコのショアラインなんか巨大なサーカステントみたいなものすごい屋根までついていて、野外の環境をしっかり楽しめるフェス会場になっている。

常設のフェス場。これは楽しそうだ。設営撤去に必要なエネルギーや資材の使い回しもできそうで、サステナブルな仕組みでもある。ここまでくると当然、近隣住民や行政、交通事業者などともに一緒に始まりをデザインする必要がある。とするならば、透明性と参加性の高さがさらに必要だ。
こういった可能性への挑戦はすでに始まっている。これも鈴木のインタビューから引用する
──ソラリズム夏2021は今年7月に初開催ですよね。「佐藤タイジが呼びかける音楽文化復興への“野外LIVEムーブメント”」ということですが、詳しくお聞かせいただけますか。
鈴木:あれは佐藤タイジくんと僕とで今動き始めてるんですけど、例えばある程度大きい1,000人規模のステージを作ろうとするとどうしても採算性が厳しいので、やり方をかなり考えなきゃいけないんです。だからソラリズムでは、各地で忘れられている常設のステージを再発見していこうと言ってるわけですよ。もしくはステージ無しでも200、300人程度で何かできるような、例えば体育館とかね。そういう小規模でも、比較的低コストでできる形をどう作るかを考えています。コロナ禍ではそれがそのまま野外で小規模で密になりにくいという条件立てのアウトラインにもなるんです。
「サブカルチャー」や「カウンター」の象徴であった知る人ぞ知るするアンダーグランドな存在だったフェスは、そこに拠り所こそあれど、もっと開かれた場所になった。いま、やり方をアップデートするときだ。もっと社会とつながり、信用を再構築するときだ。ハイライフ八ヶ岳が唯一の答えではないけど、少なくても「コロナ時代のフェスのお作法」として、誇っていいプロセスを経たと思う。
来年に向けてもこのプロセスを踏みながら進みたい。だからこそのクラウドファンディングだ。必要な予算の可視化と、支援したい人からの支援。このプロセスをもって、来年へとつなげていく。ぜひあなたにも参加してほしい。そして、来年、八ヶ岳でともに踊りたい。
来年、ここで会えるように。
Better Together.















